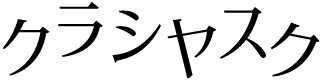都市計画法まとめ
都市計画とは
日本の国土は大きく都市計画区域と準都市計画区域、都市計画区域外の3つにまず分かれます。
この都市計画区域とは都市として総合的に整備・開発・保全を行うことが必要な区域で、原則として都道府県が指定しますが、複数の自治体にまたがる場合は国土交通大臣が指定します。
また準都市計画区域とは放置すれば将来の街づくりに支障が生じるおそれのある区域をいいます。高速道路のインターチェンジあたりのイメージです。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 準都市計画区域
- 区域区分のない区域
- その他
区域区分について
区域区分とは都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることです。
なお都市計画区域の中で市街化区域でも市街化調整区域でもないエリアは区域区分のない区域(非線引き区域)といいます。
市街化区域と市街化調整区域の定義は下記の通りです。
| 市街化区域 | すでに市街を形成している区域またはおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき地域 |
区域区分については都道府県が定めますが、任意で絶対に定めなければならないわけではありません。
ただし首都圏など大都市圏に関しては無秩序な市街化を防ぐために必ず定めなければなりません。
用途地域
用途地域とは土地の用途つまり建てられる建物を制限し、全部で13の用途地域が存在し、住居系・商業系・工業系の3種類に分けられます。
住居系の用途地域
| 第一種低層住居専用地域 | 用途地域の中で最も規制が厳しい、低層住宅の環境を保護する地域 |
|---|---|
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅の環境を保護する地域 完全に低層住宅のための地域ではない |
| 田園住居地域 | 農業の利便を増進し、低層住宅の環境を保護する地域 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の環境を保護するエリアだが、低層住宅も建てられる |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅の環境を保護するエリア |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するエリア 3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる |
| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護する地域 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなども建てられる |
| 準住居地域 | 道路の沿道としての業務の利便を増進し、住居の環境を保護するエリア |
商業系の用途地域
| 近隣商業地域 | 近隣住民に日用品を供給する商業の利便を増進するエリア 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる |
|---|---|
| 商業地域 | 主として商業の利便を増進するエリア 銀行、映画館、飲食店、百貨店など大きな工場を除いて何でも建てられるエリアで、もちろん住宅も建てられる |
工業系の用途地域
| 準工業地域 | 軽工業の工場やサービス施設など主として環境悪化の恐れのない工業の利便を増進するエリア |
|---|---|
| 工業地域 | どんな工場でも建てられる主として工業の利便を増進するエリア 住宅や店舗はOKだが、学校・病院・ホテルなどは建てられない |
| 工業専用地域 | 専ら工業の利便を増進するエリア 住宅・お店・学校・病院、ホテルなどは建てられず、工場に振り切っているエリア |
用途地域を定めることができる場所
| 市街化区域 | ○必ず定める |
|---|---|
| 市街化調整区域 | ×原則定めない |
| 非線引き区域 | ○定めることができる |
| 準都市計画区域 | ○定めることができる |
| そのほか | ×定めることができない |
補助的地域地区
補助的地域地区とは用途地域よりもさらに詳細に土地の用途を制限する地域のことです。
用途地域内にのみ定められるもの
| 特別用途地区 | 土地利用の増進、環境保護等のため用途地域の指定を補完する |
|---|---|
| 特例容積率適用地区 | 土地の高度利用のため、建築物の容積率の活用を促進する |
| 高層住居誘導地区 | 高層マンションを建てやすくするため、容積率の緩和や斜線制限・日影規制の適用除外などの特例措置が講じられる ○○住居専用地域や商業地域、工業地域・工業専用地域には定められない |
| 高度地区 | 建物の高さの限度を定める |
| 高度利用地区 | 容積率・建蔽率の限度を定める 建物の中身が高度という意味で、高さを定めるわけではない |
用途地域外にのみ定められるもの
| 特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)において、周辺環境に影響を与えかねない特定の建物の建築を制限する地域 |
|---|
どこでも定められるもの
| 特定街区 | 高さや容積率の限度、壁面の位置の制限を定める |
|---|---|
| 風致地区 | 都市の風致を維持する |
| 景観地区 | 市街地の良好な環境の形成を図る |
| 防火地域 | 市街地における火災の危険を防除するための地域として定められた地域 |
| 準防火地域 | 一般的に防火地域の周囲に指定される市街地における火災の危険を防除するための地域で、防火地域に比べて建物の制限が緩やか |
準都市計画区域での補助的地域地区
補助的地域地区は準都市計画区域で定めることが出来るものと、出来ないものに分かれます。
| 定めることが出来る | 特別用途地区 高度地区 特定用途制限地域 風致地区 景観地区 など開発の抑制が目的 |
|---|---|
| 定めることが出来ない | 高度利用地区 防火地域 準防火地域 高層住居誘導地区 特定街区 など開発の促進が目的 |
都市計画を決めるときの手続き
都市計画は原則として市町村が定めますが、方針や区域区分、大規模な都市計画事業などは都道府県が、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣が定めます。
市町村が定める場合は知事に協議をし、同意は不要です。
なお都道府県が定める場合は大臣に協議をし、同意が必要です。
| 出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
| 権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
| 法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
| 税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
| 5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
| 見直し | 20分 |
-
13:00
- 試験開始
-
宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
-
13:35
- 権利関係へ
-
権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
-
14:10
- 法令上の制限へ
-
法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
-
14:25
- 税・その他へ
-
税・その他
“税"は短くて解きやすい!
-
14:30
- 5問免除へ
-
5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
-
14:40
- 見直し
-
見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!