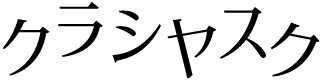防火地域と高さ制限
防火地域内の制限
防火地域とは火災の延焼を防ぐために厳しい建築制限が設けられている地域、準防火地域とは防火地域に次いで制限が厳しい地域です。
準防火地域は防火地域の周囲に指定されることが多いです。
防火地域内の建造物
| 【防火地域】 | 100㎡以下 | 100㎡超え |
|---|---|---|
| 3階以上 | 耐火 | 耐火 |
| 2階以下 | 耐火または準耐火 | 耐火 |
準防火地域内の建造物
| 【準防火地域】 | 延床面積 500㎡以下 |
延床面積 500㎡超1500㎡以下 |
延床面積 1500㎡超 |
|---|---|---|---|
| 4階以上 | 耐火 | 耐火 | 耐火 |
| 3階 | 耐火または準耐火 | 耐火または準耐火 | 耐火 |
| 2階以下 | 準耐火 | 耐火または準耐火 | 耐火 |
防火地域内の看板や広告
防火地域内の建築物の屋上に設置する場合は、主要部分を不燃材料で作るか覆う必要があります。
屋上以外に設置する場合でも、高さが3mを超えるものは主要部分を不燃材料で作るか覆う必要があります。
ちなみに準防火地域内においては広告や看板の規制はありません。
外壁の制限
防火地域または準防火地域内において、外壁が耐火構造の建築物であれば、隣地境界線に接して設けることが可能です。
つまり外壁が耐火構造であれば、民法の境界線から50cm以上の距離を保たなければならない、という規定よりも制限が緩やかになっています。
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合
もしも建築物が防火地域と準防火地域にまたがっている場合は、建築物全体に防火地域の規制が適用されます。
3つの高さ制限
建築基準法の高さ制限には大きく3つがあります。
斜線制限の詳細
斜線制限はさらに下記の3種類に分けられます。
斜線制限対象の用途地域
各斜線制限が適用される用途地域をまとめています。
どの地域にも道路はあるので、全ての地域で道路斜線制限が適用され、低層住居専用地域等はそもそも高い建物が建てられないので隣地斜線制限は適用なし、住宅街では日照が重要なので北側斜線制限は住居系の用途地域で適用されます。
| 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | |
|---|---|---|---|
| 第一種・第二種 低層住居専用地域 |
○ | × | ○ |
| 田園住居地域 | ○ | × | ○ |
| 第一種・第二種 中高層住居専用地域 |
○ | ○ | ○ |
| その他の地域 | ○ | ○ | × |
| 用途地域の 指定のない区域 |
○ | ○ | × |
日影規制
日影規制とは敷地境界線から一定の範囲に一定の時間以上の日陰を生じさせないようにする規制で、冬至日の朝8時から夕方4時までの間の測定結果を基準に建築物の高さを制限しています。
日影規制の対象地域
日影規制は適用される区域・建築物の種類が決まっていて、商業・工業・工業専用地域を除く用途地域が対象地域となります。
| 第一種・第二種低層住居専用、田園住居 | ①または②のいずれか ①軒の高さが7m超 ②3階以上 |
|---|---|
| 第一種中高層住居専用~準工業 | 高さ10m超 |
| 用途地域の指定のない地域 | 地方公共団体が条例で指定 |
| 商業・工業・工業専用 | 指定不可 |
低層住居専用地域等の高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域においての建築物の高さは10mまたは12mまでが限度で、都市計画でどちらが適用されるか定められます。