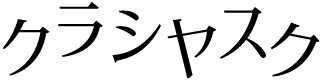抵当権とは
抵当権とは
抵当権とは債務者または第三者から特定の不動産または地上権、永小作権を担保に取り、被担保債権(担保になっている債権)が弁済されない場合にその不動産等の交換価値からほかの債権者に優先して自己の債権の満足を得る物権である。
ざっくり抵当権
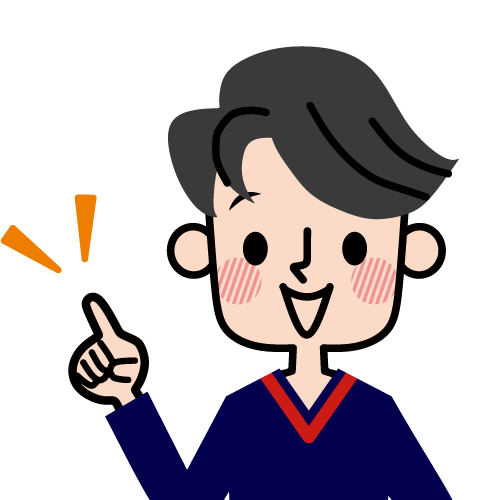
特に不動産の場合は土地や家を買うためにローンを組むことが多いと思いますが、もしも「ローンが返済できない!」となった場合にはお金を貸した銀行は担保に取っている不動産を売却してローン返済に充てることになります。
この権利のことを抵当権といい、お金を貸している銀行を抵当権者、お金を借りるために担保に出している人を抵当権設定者と言います。
抵当権の性質
| 非占有担保 | 目的物の占有・使用収益を内容としない |
|---|---|
| 価値権 | 目的物の交換価値を支配する担保物権である |
| 約定担保物権 | 抵当権は約定担保物権であり
がある |
抵当権の順位
抵当権の順位は登記の前後で決まる(民法373条)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
【民法第373条】
抵当権と登記
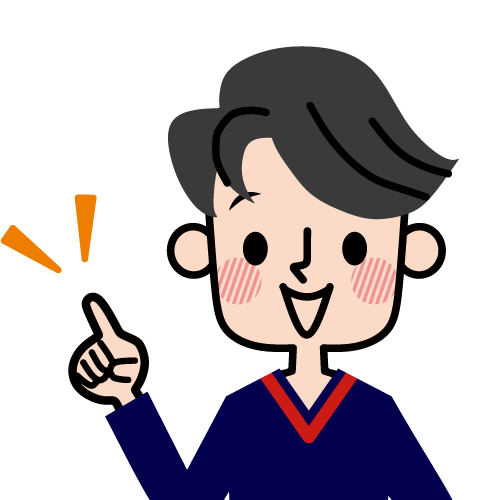
抵当権の対抗要件は登記であり、自分の抵当権を第三者に主張するためには登記が必要です。
1つの不動産には複数の抵当権が設定できるので、登記を備えた順に優先順位が決まります。
つまり早く登記した人が順位が上ということです。
なお抵当権の順位の変更も可能ですが、その場合は影響を受ける抵当権者全員の合意が必要で、その効果は抵当権者全員に及ぶこととなります。
ちなみに抵当権の順位の譲渡(先順位の人が後順位の人へ)も可能で、譲渡の場合は他の抵当権者に影響がないので、抵当権者全員の合意は不要です。
順位昇進の原則
先順位が弁済されたら、後順位が繰り上がり
順位の変更
各抵当権者同士の合意により、順位の変更が可能。
利害関係人(転抵当権者や差押え債権者など)がいる場合は、承諾が必要
順位の譲渡
抵当権の順位の譲渡とは両者が本来受けるべきだった弁済額の合計から、譲渡を受けた者が優先して弁済を受け、譲渡したものが残りの弁済を受けること。
たとえば不動産の評価額が5400万円だった場合に、第1順位の者が第3順位の者へ順位の譲渡をした場合、第2順位の者は関係がないので本来受ける弁済額と変わらず、順位の譲渡を行った者同士で本来受け取れる弁済額の中でやり取りをします。
| 本来 | 譲渡後 | |
|---|---|---|
| 第1順位 (債権2000万円) |
2000万円 | 0円 |
| 第2順位 (債権2400万円) |
2400万円 | 2400万円 (変わらず) |
| 第3順位 (債権4000万円) |
1000万円 | 3000万円 |
- 全員が本来受け取れる弁済額を書く
- 譲渡する側+される側の本来の弁済額の合計から、譲渡される側が優先して受け取り、残りを譲渡した側が受け取る
※譲渡に関係ない人の順位や受け取る弁済額に変化はしません。
順位の放棄
抵当権の順位の放棄とは両者が本来受けるべきだった弁済額の合計から、持っている債権額の割合で分配した額の弁済を受けること
たとえば不動産の評価額が5400万円だった場合に、第1順位の者が第3順位の者へ順位の放棄をした場合、第2順位の者は関係がないので本来受ける弁済額と変わらず、順位の放棄を行った者同士が同じランクになるので、持っている債権額の割合のみで受け取れる弁済額が決まります。
| 本来 | 放棄後 | |
|---|---|---|
| 第1順位 (債権2000万円) |
2000万円 | 1000万円 (割合:①) |
| 第2順位 (債権2400万円) |
2400万円 | 2400万円 (変わらず) |
| 第3順位 (債権4000万円) |
1000万円 | 2000万円 (割合:②) |
- 全員が本来受け取れる弁済額を書く
- 放棄する側+される側の本来の弁済額の合計から、それぞれの債権額の割合に応じて分配する
※譲渡に関係ない人の順位や受け取る弁済額に変化はしません。
被担保債権-範囲の制限
利息その他の定期金の請求は最後の2年分のみ
債務不履行により生じた損害賠償請求権も最後の2年分のみ
抵当権の設定対象
- 不動産(債務者所有でも第三者所有でも可)
- 地上権
- 永小作権
付加一体物
抵当不動産に付加して一体となっている物にも及ぶ(プレハブ物置・空調設備・音響設備など)
物理的に付加していない従物にも及ぶ
抵当権設定後に付加一体物となった物にも抵当権の効力が及ぶが、詐害取消請求権ができる場合は抵当権の効力は及ばない
従たる権利
借地上の建物に設定された抵当権は借地権にも及ぶ
分離物や搬出物
単に分離しただけなら経済的一体性を失ったとはいえないので、抵当権の効力が及ぶ。
なお抵当権者は搬出の禁止(妨害予防)を求めることができる
もし分離して搬出されてしまったならば、原状回復請求により元の状態に戻して競売する必要がある。
もしも第三者が即時取得してしまったならば、返還請求は出来ない。
果実
果実には原則抵当権の効力は及ばないが、もしも被担保債権について不履行があった場合は不履行後に生じた果実には抵当権の効力が及ぶ
果実から優先弁済を受けるためには担保不動産収益執行または物上代位権を行使しなければいけない。
物上代位
先取特権による目的物の交換価値の優先的支配が目的物の価値代替物にも及ぶ
目的物の価値代替物に対して物上代位する場合は、払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえが必要である。
物上代位の対象
- 損害賠償請求権・損害保険金請求権
- 売買代金債権
- 賃料債権
物上代位の例
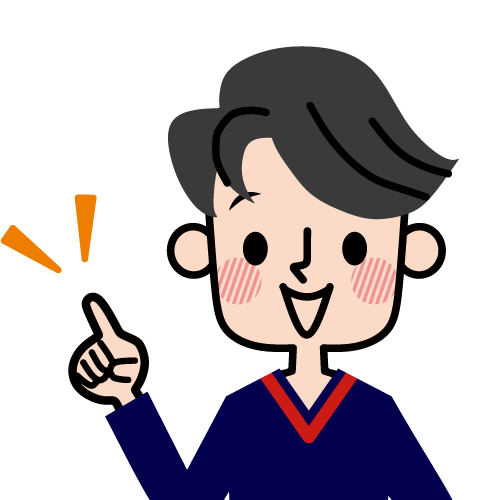
担保に取っている建物が火災で全焼してしまうと担保不動産の価値がなくなってしまいます。
もしもその不動産を火災保険に加入させていれば、抵当権者はその保険金から弁済してもらうことができます。
ただしその保険金が抵当権設定者に支払われてしまうと物上代位は出来ませんから、保険金が抵当権設定者に支払われる前に差し押さえしなければいけません。
抵当権の追及力
抵当不動産が売却されたとしても、新たな買主の元で抵当権は存続する。
つまり買主の占有下にある不動産について抵当権を実行することが可能である。
なお抵当権者は代価弁済の手段(※)によることもできる
※代価弁済とは取得した権利の代価を売主に対してではなく、抵当権者に対して支払うことで、代価弁済は抵当権者からの請求が必要。
払い渡しまたは引き渡しの前の差し押さえる理由
払い渡しまたは引き渡しの前の差し押さえることにより、物上代位の対象を特定し、一般財産と混入することを回避できる。
また払い渡しまたは引き渡しの前の差し押さえることにより、優先的に満足を得る意思を明らかにする
第三債務者は抵当権設定者に弁済することで、弁済による目的債権消滅の効果を抵当権者にも対抗が可能である。
抵当権消滅請求と第三取得者の権利
すでに抵当権が設定された不動産を購入した人を第三取得者といいます。
第三取得者はせっかく不動産を購入しても抵当権が付きっぱなしだと、いつ抵当権が実行されて所有権を失うか不安ですね。
そんな時に抵当権消滅請求を行えば、抵当権者との間で合意した金額を支払うことで抵当権を消滅させることができます。
ちなみに主たる債務者と被担保債権の保証人は被担保債権全額の弁済の義務を負っているので、抵当権消滅請求は出来ません。
つまり被担保債権の保証人となっている人が第三取得者になっても抵当権消滅請求はできないということです。
なお第三取得者が持っている権利は下記の4つがあります。
法定地上権
法定地上権とは一定の要件を満たしたときに、土地の所有者でなくてもその土地を利用できる権利のことです。
たとえば土地を借りて建物を建てていた場合に、競売によって土地の所有者が変わってしまうと、建物の所有者は土地を利用する権利がなくなり、出て行かなければいけません。
こんな不都合を回避するために建物の所有者が引き続き土地の利用を可能にしたのが法定地上権という制度です。
法定地上権が成立する要件は下記の4つです。
・抵当権設定時に土地の上に建物が存在する
・抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一である
・土地と建物の一方または両方に抵当権が存在する
・抵当権が実行されて土地と建物の所有者が別々になる
一括競売
一括競売とは土地に対する抵当権が設定された後にその土地に建物が建てられた場合に、土地だけでなくその上の建物までも一括で競売できる制度です。
あくまでも抵当権は土地にしか設定されていないので、優先的に弁済を受けられるのは土地代金からのみです。
根抵当権とは
普通の抵当権はたとえば"今回3000万円貸して"といった感じで「額」を決めるのに対し、根抵当権とは"5000万円を限度に何回かに分けて貸してほしい"といった感じで「枠」を初めに設定しておくイメージです。
つまり借り入れを何回繰り返しても、合計額が初めに設定した「枠」を超えなければわざわざ抵当権を設定し直す必要がありません。
この「枠」のことを極度額といいます。
元本確定
普通の抵当権と根抵当権の違いの1つは「元本確定」が必要なことです。
普通の抵当権であれば最初から3000万円などと確定していますが、根抵当権は極度額が決まっているだけなので、最終的に"実際借りたのは4500万円でした"といった形で確定させる必要があります。
元本確定後の根抵当権は普通の抵当権と性質は同じとなり、付従性や随伴性があります。
また元本確定がないと抵当権の実行が出来ません。
- 元本確定後の根抵当権は普通の抵当権と同じ性質になる
- 根抵当権者はいつでも元本確定が出来る
- 根抵当権設定者は元本確定期日の設定がない場合、根抵当権設定時から3年を経過すると元本確定の請求ができる
請求時から2週間後に元本が確定する - 元本確定までは債権者は転抵当以外の処分が出来ない
極度額の譲渡は可能