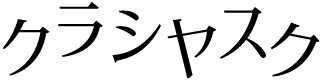権利関係-保証と連帯債務
保証契約
保証契約とは債務の保証のために保証人になる人と債権者が結ぶ契約のことです。
保証人になった人は債権者に対し、保証の対象となる債務について、主たる債務者が負う債務と同種の債務を負担します。
つまりもしも主たる債務者が支払わなかったときは、保証人が代わりに支払わなくてはいけません。
これを保証債務といいます。
保証契約の要件
下記3つが保証契約の要件です。
- 主たる債務がある
- 債権者との間で保証契約を結んでいる
- 書面で契約している
保証債務の性質
催告の抗弁
債権者が保証人にいきなり履行請求してきたときに、「いやいやまずは主たる債務者に取り立ててよ!」と履行を拒むことができます。
検索の抗弁
債権者が債務者、保証人の順番で履行請求してきたとしても下記①と②を証明した時は、まず主たる債務者へ執行するよう求めることができます。
- 主たる債務者に弁済できる資力がある
- 主たる債務者への執行が容易である
保証債務の範囲
保証契約の締結後に主たる債務が増えたとしても、保証債務まで増えることはありません。
つまり保証人としては保証契約を結んだ時の債務のみを保証すればよく、知らないうちに保証債務が増えることはないということです。
保証人の求償
求償とは自分が払った金銭を債務者に請求することで、保証人が弁済した時はその分を主たる債務者に求償することができます。
求償が制限されるとき
ただし下記の場合は保証人の求償が制限され、主たる債務者が現に受けた利益を限度にしか求償できません。
- 保証人が弁済期前に弁済した
- 保証人が弁済する前に主たる債務者へ通知していない
根保証契約
根保証契約は不特定の債務を保証する保証契約ですが、元本の確定期日が到来すると保証の元本が確定し、それ以降に生じた債務については保証の対象外となります。
個人根保証と法人根保証
この額まで保証するという極度額について、個人根保証については定めておく必要があり、法人根保証では不要です。
また個人根保証の場合は元本も下記の場合は確定期日が到来するより前に確定することがあります。
- 個人根保証の債権者が保証人に強制執行したとき
- 主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき
事業のための債務の保証
事業のための債務は金額が大きくなりがちですから、個人が事業のための貸金債務を保証するときは契約締結の1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成しなくてはいけません。
連帯債務とは
連帯債務が成立すると、債権者はそのうち1人に対してもまたは全員に対しても、債務の全部または一部の履行を請求できます。
求償の例
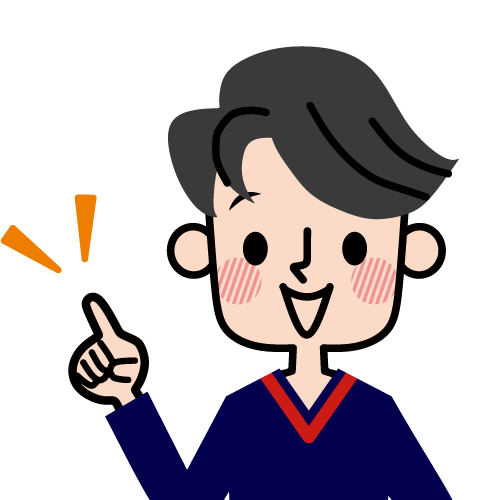
Aに対してBとCが100万円の連帯債務を負っているとして、BとCはAから請求されるとそれぞれ100万円全額を支払う必要があります。
もしもBが100万円を支払ってCが1円も支払わなかった場合、BはCに求償することができます。
このとき別段の意思表示がない時は各債務者は等しい割合での義務を負いますから、BはCに対して100万円の半分の50万円を求償できるわけです。
ちなみにBが100万円全額ではなく20万円だけAに支払ったときは、同様に半分の10万円の求償が可能です。
相対効の原則
相対効の原則とは連帯債務者の1人に生じた事由は、原則として他の債務者に影響がないことをいいます。
たとえば債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除したとしても、他の連帯債務者の債務は免除されません。
絶対効の例
下記4つの場合は絶対効として他の連帯債務者に影響を及ぼします。
| 出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
| 権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
| 法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
| 税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
| 5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
| 見直し | 20分 |
-
13:00
- 試験開始
-
宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
-
13:35
- 権利関係へ
-
権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
-
14:10
- 法令上の制限へ
-
法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
-
14:25
- 税・その他へ
-
税・その他
“税"は短くて解きやすい!
-
14:30
- 5問免除へ
-
5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
-
14:40
- 見直し
-
見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!