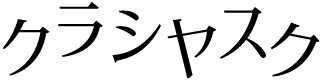借地借家法
借地借家法の適用と効果
建物所有目的で土地を借りるときは借地借家法が適用され、土地の賃貸借の内容が借地権者にとって有利なものとなります。
逆に駐車場や資材置き場など建物所有目的でない場合は、借地借家法は適用されません。
借地権の効果
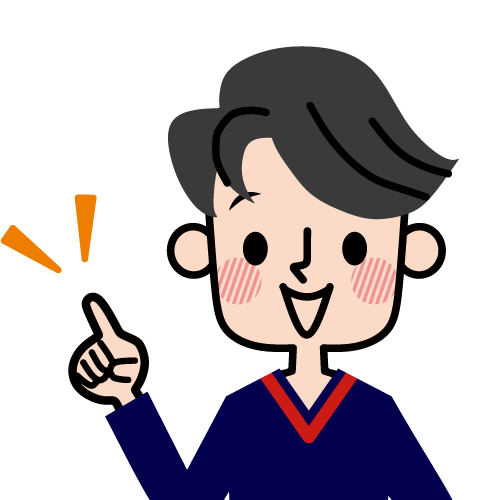
借地借家法が適用されると、借地借家法上の条件より借主にとって不利な条項は無効となり、借地借家法上の条件が契約内容となるワケです。
たとえば借地借家法法上の借地権の存続期間は最低30年ですが、これより短い期間で貸主と借主が合意しても無効となり、30年での契約となります。
借地権の対抗要件
借地権の対抗要件は下記2点のいずれかです。
- 借地権の登記がある
- 借地上に自分名義の建物がある
ひとこと借地権
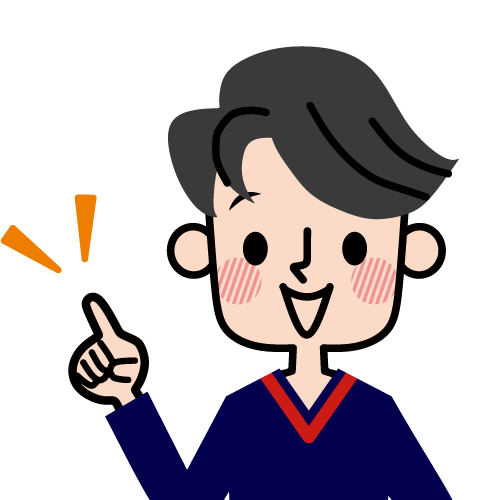
民法上は賃借権を第三者に対抗するためには賃借権の登記が必要ですが、借地借家法では借地権の登記がなくても、その土地の上に自分名義の建物が立っていれば、登記がなくても第三者へ対抗ができます。
借地権の登記は貸主・借主の両者で行う必要がありますが、貸主にとって借地権の登記義務はないので、協力してもらえないケースも多いです。
そんな場合でも自分名義の建物さえ立っていれば対抗要件を具備できるので、所有者が変わっても権利の主張が簡単です!
借地権の更新方法
借地権の更新がなされるのは下記の3つの場合です。
請求更新を拒否したい場合は借主の請求に対して、また法定更新を拒否したい場合は土地使用を続けることに対しての異議を遅滞なく主張する必要がありますが、いずれも正当な事由がない限り更新を拒否することができません。
借地権の更新の効果
借地権が更新されると存続期間は初回の更新後は20年、その後は10年となります。
そのほかの契約内容は元の条件と同じです。
建物買取請求権
建物買取請求権とは借地権者が契約期間満了時に、貸主に対して建物を買い取るよう請求できる権利です。
借主が建物買取請求権を行使すると、たとえ貸主が合意しなくても両者の間に売買契約が成立し、貸主が建物の代金を支払わない場合は借主は土地を引き渡さなくて良いとされています。
建物買取請求権の要件
- 借地権の期間が満了したこと
- 契約の更新がないこと
定期借地権
定期借地権とは存続期間を50年以上とし、契約の更新がない旨を定めた借地権のことで、契約の更新がない旨は書面により行う必要があります。
定期借地権の特徴
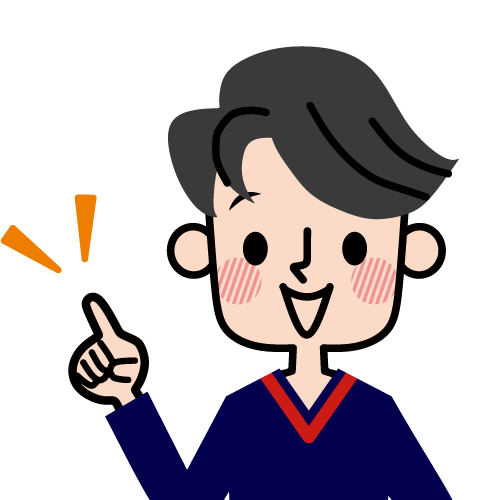
普通の借地権と定期借地権の違いとしては
・契約の更新が出来ない
・建物買取請求権が出来ない
ことです!
借地上の建物の滅失と再築
もしも借地上借地上の建物が滅失してしまっても借地権は消滅しません。この場合借地権者は建物を再築することができますが、貸主の承諾がある場合とない場合で扱いが異なります。
再築について承諾がある場合
借地権の期間満了前に建物が滅失し、再築に当たって貸主の承諾がある場合は、①承諾があった日または②建物が再築された日のいずれか早い日から20年間存続します。
なお借地権者が再築の通知をして2か月以内に貸主が異議を述べない場合は、承認があったものとみなされます。
再築について承諾がない場合
再築に当たって貸主の承諾がない場合は再築は出来ますが、当初の契約期間で満了となります。
ただし契約期間満了の後に建物が存在していれば法定更新がなされ、建物が存在しなければ契約期間満了で終了となります。
| 期間 | 目的 | 法定更新 | 書面 | |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸借(民法) | 上限50年 | 制限なし | 同一条件で 推定 |
×不要 |
| 借地権 | 30年以上 | 制限なし | ○あり | ×不要 |
| 定期借地権 | 50年以上 | 制限なし | ×なし | ○必要 |
| 事業用 定期借地権 |
10年以上50年未満 | 事業用のみ | ×なし | ○公正証書 |
| 建物譲渡特約 付き借地権 |
30年以上 | 制限なし | ×なし | ×不要 |
借家契約
住居に限らず、建物の賃貸借契約であれば、原則として借地借家法が適用されますが、一時的に利用することが明らかであれば、民法の賃貸借が適用されます。
借地借家法が適用されると、借主にとって不利な条件での契約が出来なくなり、借地借家法の条件を遵守しなければなりません。
たとえば期間の定めのない契約をした場合、民法の規定では解約を申し入れて3か月後に契約終了となりますが、借地借家法が適用されると解約の申し入れから6ヶ月が経たないと契約が終了しません。
賃借権の対抗要件
借りている建物の所有者が変わった場合、借主が元の貸主から建物の引き渡しを受けているだけで、新しい持ち主にも対抗することが可能です。
賃料の増減
特約がない場合は賃料について増減額請求が認められており、契約期間中に増額もしくは減額の請求ができます。
賃料の増減額については下記3点が考慮されます。
- 土地または建物に対する税金の負担
- 土地または建物の価格の変更や物価などの増減
- 近傍同種建物の借賃との差異
賃料の増減額の特約
- 賃料を減額しない特約:無効
- 賃料を増額しない特約:有効
賃料を減額しない特約は借主にとって不利なので無効となり、もしも減額しない特約があっても貸主に減額請求をすることが可能です。
逆に賃料を増額しない特約は借主に有利なので、そのまま有効となります。
借家契約の終了
期間の定めがある場合
期間の定めがある場合に契約満了により契約終了するには下記の条件を満たす必要があります。
- 期間満了の1年から6か月前までに契約更新しない通知を借主に出すこと
- その際に正当な理由があること
- 期間が満了すること
- 期間満了後にも借主が使用し続けた場合に、遅滞なく異議を述べること
期間の定めがない場合
期間の定めがない場合に契約満了により契約終了するには下記の条件を満たす必要があります。
- 解約を申し入れること
- その際に正当な理由があること
- 解約の申し入れから6か月が経過したこと
- 期間満了後にも借主が使用し続けた場合に、遅滞なく異議を述べること
契約終了のポイント
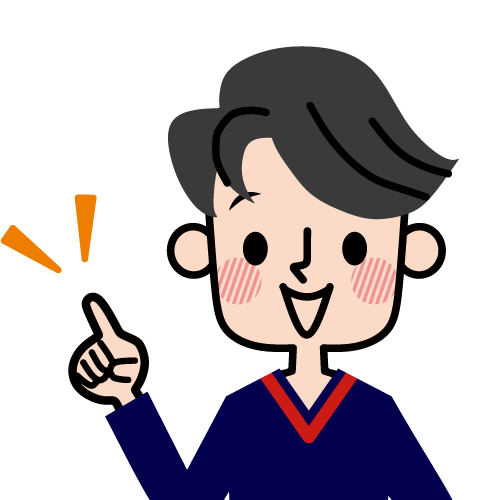
正当事由が必要なワケは、借主が理由なく追い出されることがないよう保護するためです。
また正当事由があり終了となったとしても、6か月以上の引っ越し準備期間を用意しているところがポイントです!
借家契約の更新
上記の要件を満たされずに借家契約が更新された場合は、前と同じ内容で、一律に期間の定めのない契約となります。
定期建物賃貸借契約
上記の借家契約と異なり、借主側が更新する必要がないという場合は定期建物賃貸借契約を結ぶこともできます。
定期建物賃貸借契約を締結する要件は下記の3つです。
- 書面または電磁的記録で契約する
- 契約書とは別に期間満了後に更新せず契約終了となる旨が記載された書面または電磁的記録を交付する
- ②の交付の時に期間満了後に契約更新がない旨を説明する
なお貸主は借主に対して期間満了の1年前から6か月前までに契約終了の通知を行う必要があります。
ただし借主側が終了させたいときはこの通知がなくても契約終了させることができます。
定期建物賃貸借契約の特徴
定期建物賃貸借契約が借家契約と異なり、下記の特徴があります。
- 期間満了により契約が終了する
- 賃料減額請求が出来ない特約も可能
- 一定の条件(※)で借主からも中途解約が可能
※床面積が200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない理由で生活の本拠とすることが困難になったこと
当日のポイント
| 出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
| 権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
| 法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
| 税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
| 5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
| 見直し | 20分 |
-
13:00
- 試験開始
-
宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
-
13:35
- 権利関係へ
-
権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
-
14:10
- 法令上の制限へ
-
法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
-
14:25
- 税・その他へ
-
税・その他
“税"は短くて解きやすい!
-
14:30
- 5問免除へ
-
5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
-
14:40
- 見直し
-
見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!