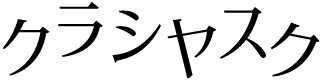宅建業法 8種制限とは
8種制限とは
ざっくり8種制限
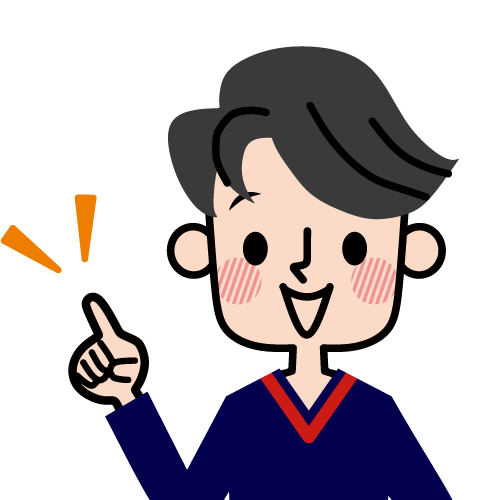
8種制限は宅建業者が自ら売主となる場合に、知識・経験の差により買主に不利な契約が成立してしまわないように課せられる8種の制限のことをいいます。
売主が宅建業者で買主が宅建業者でない一般のお客さんであるときに、契約内容や解除に関する特定の制限が課されています。
8種制限の詳細
- 他人物売買の制限
- 所有権留保の禁止
- 損害賠償額の予定の制限
- 担保責任の特約の制限
- 手付の額・性質
- 手付金等の保全措置
- 銀行等による保証
- 保険事業者による保証保険
- 【完成物件のみ】指定保管機関(※)による保管
- 一定額かつ一定割合以下
- 買主の所有権が登記されたとき
- 割賦販売における解除の制限
- クーリングオフ
- 宅建業者の事務所
- 専任の宅建士を置くべき案内所(土地に定着した建物のみ)
- 売主が依頼した代理・媒介業者の①②の場所
- 買主が自ら申し出た自宅または勤務先
- 買主の氏名および住所
- 売主の商号または名称および住所・免許証番号
- 書面によりクーリングオフを行うことができること
- 損害賠償請求等の禁止
- 効力の発生時期
- 手付金等の返還
-
13:00
- 試験開始
-
宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
-
13:35
- 権利関係へ
-
権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
-
14:10
- 法令上の制限へ
-
法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
-
14:25
- 税・その他へ
-
税・その他
“税"は短くて解きやすい!
-
14:30
- 5問免除へ
-
5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
-
14:40
- 見直し
-
見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!
宅建業法では一定の場合を除き、他人が所有する宅地・建物の取引を禁止しています。
もしも予約や契約を受けた後で宅建業者が物件を取得できなかった場合に、お客さんが大きな損害を被るので、宅建業者自身が所有していない宅地や建物について自ら売主となる売買契約や予約を締結することができません。
他人物売買についての例外があります。
・宅建業者が当該宅地・建物の取得契約を締結しているとき
※停止条件付き契約を除く
・宅建業者が当該宅地・建物を取得することが明らかで、国土交通省令・内閣府令で定めるとき
・未完成物件の売買で、手付金の保全措置が必要な場合に、その措置が講じられているとき
所有権留保とは割賦販売の契約を結んだ時に、全額の支払いが完了するまで売主に所有権が留保される特約で、宅建業法では一定の場合を除き、この所有権留保を禁止しています。
下記の場合は所有権留保が可能です。
・宅建業者が受け取った金額が代金の10分の3以下のとき
・買主が宅地・建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権などの登記を申請し、またはこれを保証する保証人を立てる見込みがないとき
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償を予定したり違約金を定めることができますが、損害賠償額の予定額と違約金を合算した額が代金の10分の2を超えてはならず、代金の10分の2を超えた分は無効となります。
損害賠償を予定しない場合
損害賠償額の予定を定めない場合は、実際に発生した損害額を請求することが可能ですが、契約違反によって生じた現実の損害が基準となり、その損害額を裁判などで証明する必要があります。
ちなみに実際の損害額が売買代金を超えても問題ありません。
売買した不動産が契約内容に合っていないときに売主が負う責任である担保責任に関する特約が、消費者に不利にならないよう制限されています。具体的には買主にとって民法の規定よりも不利な特約を定めることはできません。
売主が契約に適合しない物件を引き渡した場合、担保責任として民法では下記4つの権利を買主が売主に行使できます。
【追完請求権】
修理や交換、不足分の引き渡しを求める権利
【代金減額請求権】
契約不適合の程度に応じて支払う代金を減額できる権利
【損害賠償請求権】
契約不適合により生じた損害賠償を求める権利
【解除権】
重大な契約不適合のとき契約解除できる権利
ちなみに種類または品質に関する不適合で売主の責任を追及するためには、買主が不適合の事実を知ってから1年以内に通知する必要があります。
通知の期間の例外
宅建業法では民法より買主にとって不利な特約を定めることができませんが、通知の期間の例外があり、引き渡しの日から2年以上の期間内となる特約を定めることは可能です。
つまり買主の認識ではなく、引き渡し日が基準となっている点が民法と異なっています。
制限に反した場合の扱いは?
もしも担保責任の特約の制限に反する特約を結んだ場合は、その特約が無効となり、代わりに民法の規定が適用されます。
もちろん民法の規定よりも買主にとって有利な特約はそのまま有効です。
消費者が不利にならないよう、手付金の額や性質に制限を設けています。
手付の種類
| 証約手付 | 契約成立を証明するための手付金 |
|---|---|
| 連約手付 | 相手方に債務不履行があった場合の違約金のための手付金で、契約違反の場合は没収となる |
| 解約手付 | 契約締結後でも一定の条件下で契約解除できる権利のある手付金 |
手付の性質の制限
宅建業法では売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合には手付は常に解約手付として扱うよう定めています。
したがってどんな性質の手付であっても、売主・買主ともに下記の手続きを踏めば契約の解除ができます。
・買主は手付を放棄することで契約解除が可能
・売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除が可能
ただしすでに引き渡しや移転登記、中間金の支払いなど相手方が契約の履行に着手した後は、上記の方法でも契約解除は出来ません。
手付の額の制限
宅建業法では売買契約において手付金の額が代金の10分の2を超えてはならないと定めており、もしも代金の10分の2を超えてしまうと超えた分のみ無効となります。
ちなみに売主・買主間で合意があったとしても代金の10分の2を超える手付金の受領は認められません。
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金や中間金など契約締結から物件の引き渡しまで前までに買主が支払う金銭を受け取るためには第三者による保証や保管といった手付金の保全措置が必要です。
手付金の保全措置は手付金等の額や契約締結時に物件が完成しているかにより異なります。
・保全措置の方法
手付金等の保全措置には下記の3つの方法があります。
※指定保管機関とは国土交通省が指定する"全国宅地建物取引業保証協会"と"不動産保証協会"の2つで、未完成物件では指定保管期間による保管は利用できません。
・保全措置が不要な場合
下記の場合は手付金等の保全措置が不要です。
【完成物件】売買代金の10%以下かつ1,000万円以下
【未完成物件】売買代金の5%以下かつ1,000万円以下
保全措置を行わない場合
宅建業者が手付金等の保全措置が必要なのに行わない場合は、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。
宅地・建物購入のための分割払いの義務が履行されない場合に、厳しい要件を満たさなければ、支払い遅延を理由とした契約の解除が出来ないようになっています。
分割支払いの義務が履行されない場合、30日以上の期間を定めて支払いを書面で催告したうえで、その期間内に履行されなかったときに契約の解除ができます。
クーリングオフとは消費者が冷静に判断できない状況で契約してしまった際に、一定期間内であれば契約を解除できる制度で、宅建業法にも規定されています。
下記の事務所等以外で申し込みや契約を行った場合、クーリングオフが可能となります。
ちなみに申込み場所と契約場所が異なる場合は、契約の申し込みをした場所で判断します。
クーリングオフできる期間
クーリングオフができる期間は書面でクーリングオフの権利が告げられた日を含めて8日以内です。
なお書面でなく口頭や電子メール等でクーリングオフを告げられた場合は無期限で契約解除が可能です。
クーリングオフできない場合
売買契約が完了した場合はクーリングオフできません。
具体的には“申込者が宅地・建物の引き渡しを受けた"かつ"代金の全額を支払った"場合です。
クーリングオフを告知する書面には下記を記載します。
クーリングオフがなされた場合に宅建業者が違約金や損害賠償の請求をすることは禁止です。
クーリングオフがなされると契約は白紙になりますので、売主は買主が支払った手付金や契約金などすべての金銭を速やかに返還しなければいけません。
なおクーリングオフでの解約は買主がクーリングオフの書面を発送した時点で即座に契約解除の効力が生じ、売主に届いたタイミングは関係ありません。
| 出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
| 権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
| 法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
| 税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
| 5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
| 見直し | 20分 |
宅建業法